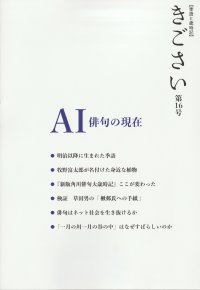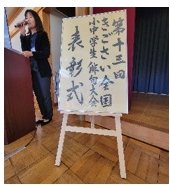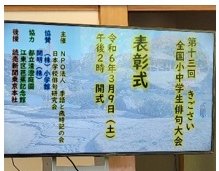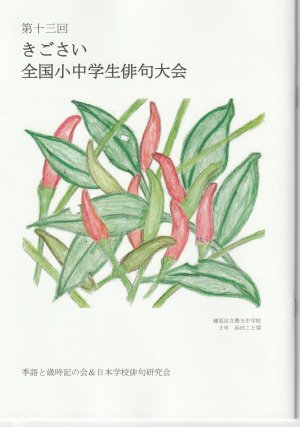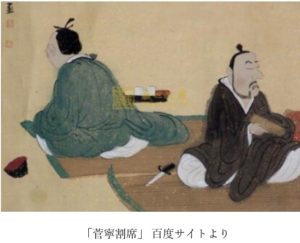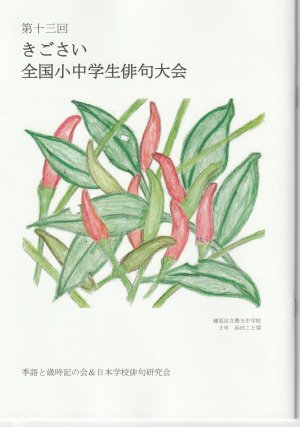
【大賞】
あせいっぱいぼくのからだであそんでる
土佐市立高岡第一小学校 五年 関 隆佑
【学校賞】
土佐市立高岡第一小学校
山口大学教育学部附属光中学校
【奨励賞】
江東区立第二亀戸小学校
大分市立大在小学校
小山正見 選
【特 選】
夏祭りみこし空まで持ち上げる
静岡学園中学校 三年 宮村 圭
コロナ感染が下火になり、三年ぶりのお祭りが弾けるように各地で行われた。神輿が町をうねり、威勢のよいかけ声が響いた。そこには日常が戻って来た喜びが込められている。
マイルール白線たどる春の道 足立区立島根小学校 五年 杉瀬 葵
学校の登下校、石を蹴り続けて歩いたり、線の上から外れないように歩いたり・・・一人でそんな遊びをしたことがある。自分だけの「マイルール」を決めた遊びなのだ。こどもはすべてを遊びにしてしまう天才だ。
青空を貸し切りにして運動会 江東区立有明小学校 六年 安井彬人
運動会の天候だけは、先生方や保護者の力ではどうにもならない。ところが、当日は素晴らしい秋晴れ。「やった!」と叫びたくなるほどだ。地上では素敵な演技が繰り広げられたに違いない。
【入 選】
花束のようにかかえる稲の束 大分市立大在小学校 五年 白井海翔
咲きたての桜のような十二歳 豊島区立西池袋中学校 三年 石山結華
風船が空に吸われて終戦日 大分市立大在小学校 五年 秦野琥羽
しんしんと雪の音色がふりつもる 京都女子大学附属小学校 三年 下園紗代
あせいっぱいぼくのからだであそんでる 土佐市立高岡第一小学校 五年 関 隆佑
点Pに点Q追加小鳥来る 仙台市立郡山中学校 三年 石川寿々
終戦日影も子どももみな消えた 大分市立大在小学校 五年 松尾彩希
うらがえるセミのちかくをおそるおそる 千代田区立九段中等教育学校 二年 久木元秀至
新米の一つ一つの物語 江東区立扇橋小学校 六年 越島優奈
ぱくぱくときんぎょものいうことがある 土佐市立高岡第一小学校 二年 田中詩乃梨
【佳 作】
あきのはれジャングルジムにぶらさがる 江東区立数矢小学校 一年 横澤吾郎
夕立といっしょに帰る午後三時 江東区立第一亀戸小学校 五年 瀧澤彩妃
まく種は亀戸大根秋日和 江東区立第二亀戸小学校 四年 川﨑佑馬
青森で最初は雪をかく仕事 江東区立浅間竪川小学校 四年 清野太翔
せみとったぼくよりよろこぶおじいちゃん 京都女子大学附属小学校 二年 浮村聡一
夜食とる母の愛情重すぎる 仙台市立郡山中学校 三年 黒田春美
髪洗ふ今日の失敗流れゆく 鹿児島市立坂元中学校 二年 住本愛恵
秋驟雨ノイズ混じりのレスポール 大阪市立都島中学校 三年 甲田莉久
耕せば土を跳び越す雨蛙 お茶の水女子大学附属中学校 三年 由宇弘賢
東照宮博識になる秋うらら 江戸川区立北小岩小学校 六年 吉羽悠人
どんぐりのサイズのちがうぼうしかな 江東区立第二亀戸小学校 四年 戸倉煌希
アンカーは君に任せた赤とんぼ 江東区立数矢小学校 五年 藤本亮馬
るすばんの庭にゆれてる秋ざくら 足立区立西新井小学校 三年 加藤 絢
秋の空まがってにげるおにごっこ 葛飾区立新宿小学校 四年 手嶋琉斗
秋の空十秒まったらかげおくり 葛飾区立新宿小学校 四年 長野璃々
髙田正子 選
【特 選】
いますぐにはしりだしたいとかげかな 世田谷区立桜丘小学校 三年 濱﨑 葵
このとかげは、作者が自分を見ていることを知っているのでしょう。のどのあたりがドキドキと大きく動いています。つかまえようと手を伸ばしてきたら、さっと逃げるからな、と言わんばかりに小さな眼が動きます。とかげの身になって詠み切ったところが楽しい句です。
ドッカーンほえているんだ大花火 土佐市立高岡第一小学校 四年 中平琉輝矢
中止が続いていた花火大会が次々に再開された二〇二三年でした。河原や海辺へ出かけて、本物の打ち上げ花火を見上げた作者でしょう。テレビで観るのとは違ってすごい迫力です。全身でとらえた花火は猛獣のようにほえていました。「ほえる」が光る句です。
満月へ道がつながるはしの上 江東区立川南小学校 六年 伊藤 翔
作者は今どこかの橋を渡ろうとしています。真正面には大きな満月。月の光を受けて橋は白い道のようです。このまままっすぐ渡っていくと月まで行けるかもしれない。そんな気分になったのでしょう。「道がつながる」と言い切ったところがすばらしいです。
【入 選】
キューピーのあたまみたいなミニトマト江東区立豊洲北小学校 二年 村上杏那
春の朝鳥がきれいにしゃべってる江東区立東砂小学校 六年 髙橋想來
夏祭りみこし空まで持ち上げる静岡学園中学校 三年 宮村 圭
天の川空が遠くてつかめない鹿児島市立坂元中学校 三年 子島悠飛
赤いみちたどるように林檎剥く学習院女子中等科 三年 西村理子
ひまわりはアップルパイのかおみたい土佐市立高岡第一小学校 三年 野瀬悠吏
ばあちゃんち跣であるく木の廊下山口大学教育学部附属光中学校 三年 長沼美波
のぼりぼうたかくのぼれたあきのそら江東区立第一亀戸小学校 一年 田中奏多
青空を貸し切りにして運動会江東区立有明小学校 六年 安井彬人
こおろぎは静かになったら鳴いてくる江東区立東砂小学校 五年 川鍋彩羽
【佳 作】
風船が空に吸われて終戦日 大分市立大在小学校 五年 秦野琥羽
ベランダの手すりをはじく春の雨 町田市立南中学校 二年 山口花音
雨つぶは涙みたいにふって来る 南あわじ市立志知小学校 三年 船本紗世
庭先のあじさい一輪雨のにおい 鹿児島市立坂元中学校 一年 小野由莉子
はくちょうがぐんぐんぐんとおよいでる 美濃加茂市立太田小学校 二年 今井蒼音
ばあちゃんにやきいもおいしくやけました 高岡市立伏木小学校 四年 井菜々海
秋探し寂しい顔のすべり台 学習院女子中等科 三年 皆川彩葉
ラムネ瓶滴る水に青い空 枚方市立小倉小学校 五年 山本宇架
青森で最初は雪をかく仕事 江東区立浅間堅川小学校 四年 清野太翔
藍色の額紫陽花と雨の色 山口大学教育学部附属光中学校 三年 梶本心咲
秋日和よそいきのふくなびかせる 江東区立豊洲北小学校 四年 別所和佳奈
こすもすがゆれるわらっているみたい 高岡市立伏木小学校 一年 今井 尊
弟が生意気になる夏休み 大分市立大在小学校 五年 太田美結
校ていに小さな風の九月かな 足立区立中川北小学校 五年 山地光星
カーテンのすきまの光春近し 江東区立豊洲北小学校 四年 満行悠衣
長谷川櫂 選
【特 選】
父がつくる雑煮の味は母の味山口大学教育学部附属光中学校 三年 久保めぐみ
お母さんのいない家族を想像した。雑煮もお父さんが作るのだが、お母さんが作っていた雑煮の味がする。どういう事情かわからないが、複雑な背景を表現している。たまたま、お父さんが雑煮を作っただけかもしれないが、それならそれで、また別の味わいがある。
終戦日影も子どももみな消えた大分市大在小学校 五年 松尾彩希
ウクライナやガザで大人たちが戦争をしている。そして誰よりも犠牲を強いられているのが、子どもたちという現実を前にして、子どもたちが戦争に関心をもつ、戦争という言葉を日常語として使う。それはしかたないことであるよりは、そうあるべきだろう。こんな時代、子どもの世界だけが楽園ではいられない。
あせいっぱいぼくのからだであそんでる土佐市立高岡第一小学校 五年 関 隆佑
身体中の汗の玉を遊んでいるととらえたところ。「ぼくのからだ」を遊び場にして。汗の玉一つ一つが命あるものに見えてくる。
【入 選】
いつもより兄弟でいる夏休み 大分市立大在小学校 五年 篠原奏太
けんかして心の中がうろこ雲 江東区立第二亀戸小学校 四年 中島颯希
鯉幟どこにもいけない受験生 玉城町立玉城中学校 三年 宮本徠翔
座禅して頭の中も雪景色 古河市立総和中学校 三年 小岩大和
何気ない親の一言稲光 玉城町立玉城中学校 三年 木村優峨
恐竜がたんじょうすれば夏がくる 都立立川国際中等教育学校附属小学校 二年 萩野 優
風にのる落ち葉は空のぼうけんか 江東区立第二亀戸小学校 一年 松坂美空
夜食とる母の愛情重すぎる 仙台市立郡山中学校 三年 黒田春美
せんぷうきいくないくなとくびをふる 西宮市立春風小学校 二年 安部穂乃香
び生物見ているつゆのけんびきょう 高岡市立伏木小学校 四年 阿久津結羽
【佳 作】
はざくらのはのかげわいわいおどってる 江東区立平久小学校 三年 松本歩花
大空をいろんな風で泳ぐ鯉 足立区立花畑第一小学校 六年 綱島汰一
口の中湯気ふく焼き芋活火山 江戸川区立南篠崎小学校 四年 柳沢悠斗
どんぐりのサイズがちがうぼうしかな 江東区立第二亀戸小学校 四年 戸倉煌希
夏舞台汗の量だけ変われるか 大阪市立都島中学校 三年 上江洲つばめ
ひがん花花びらおちてもえている 江東区立第一亀戸小学校 二年 三浦永都
サングラス外すと世界光りだす 麗澤中学校 三年 大滝友翔
終わりゆく中三の日々桜かな 浜松市立北部中学校 三年 古𣘺瑞稀
いますぐにはしりだしたいとかげかな 世田谷区立桜丘小学校 三年 濱﨑 葵
戦争だ我が我がと扇風機 玉城町立玉城中学校 三年 藤川廉真
画用紙にくっついているせみのから 江東区立第二亀戸小学校 三年 金指 蓮
夕立といっしょに帰る午後三時 江東区立第一亀戸小学校 五年 瀧澤彩妃
いやなこと全部ふきとぶせんぷうき 江東区立第二亀戸小学校 六年 青山孟生
初日だけ気合が入る夏休み 江東区立平久小学校 六年 西 篤輝
たいやきの少しとまどう一口め 仙台市立郡山中学校 三年 奥山詩音
日本学校俳句研究会が選ぶ二十句
バレンタイン余ったチョコと嘘をつく 山口大学教育学部附属光中学校 三年 山根温花
バレンタインデーに「本命」と言って渡すことができず、「余った」チョコと嘘をついてしまった。照れてくさい気持ちがとても伝わってきます。下の句の「嘘をつく」と表現したところに気持ちが集約されている一句です。
せんせいにあかちゃんできるあきのそら 江東区立豊洲北小学校 一年 太田真帆
大好きな先生に赤ちゃんが生まれると知り、嬉しいけれど、寂しい。秋の空のように晴れ渡っているけれど、同時に切なさを感じる。一言では表せない気持ちと、季語とが響き合っている句です。
夜食とる母の愛情重すぎる 仙台市立郡山中学校 三年 黒田春美
試験勉強をする作者に対して、お母さんが夜食を届けます。母の子を思う愛情と、いつの間にか成長している作者の母を思う微妙な心情との交錯が伝わってきます。
せみとったぼくよりよろこぶおじいちゃん 京都女子大学附属小学校 二年 浮村聡一
作者は祖父に蝉捕りの極意を学んだのでしょう。木に止まっている蝉をうまく捕獲できた喜びは格別なもの。自分より興奮している祖父とそれを見つめる作者。二人の関係がよく伝わってきます。
風船が空に吸われて終戦日 大分市立大在小学校 五年 秦野琥羽
風船は希望・平和な日常・人の命などの象徴でしょう。その風船が「空に吸われる」という表現に、戦争は終わったけれど、戦争によって大切なものをなくした喪失感や虚しさが伝わってきます。
かくれんぼトンボはぼくを見つけてる 徳島文理小学校 四年 中村健汰
かくれんぼをしている時のこと。鬼役の友だちは自分のことをまだ見つけていませんが、トンボとは静かに目が合っています。息をひそめて隠れている様子がよく表現されています。
引っぱるなふとんのとりあい二回戦 江戸川区立北小岩小学校 四年 内田花音
兄妹で布団の取り合いをしているのでしょうか。寒い時期は、布団がより恋しくなります。近くで寝ている家族と、ふとんを取り合う微笑ましい様子が想像できます。
弟が生意気になる夏休み 大分市立大在小学校 五年 太田美結
夏休みになり、弟と過ごす時間が長くなる作者。家で、旅先で、様々な場面で、弟の成長を感じます。「生意気になる」の表現に弟への複雑な気持ちが伝わる一句です。
五月雨弁慶眠る巌かな お茶の水女子大学附属中学校 三年 鈴木文華
修学旅行で平泉の中尊寺に行ったのでしょうか。弁慶の墓の前で歴史に思いを馳せている様子が目に浮かびます。「五月雨」の季語が弁慶を偲んでいるようです。
ばあちゃんち跣であるく木の廊下 山口大学教育学部附属光中学校 三年 長沼美波
おばあちゃんのお家には、昔ながらの木の廊下があるのでしょう。「跣」の足裏の木の感触。少しひんやりとした心地よい感触は、おばあちゃんの思い出と共にずっと心に残ることでしょう。
髪洗ふ今日の失敗流れゆく 鹿児島市立坂元中学校 二年 住本愛恵
「髪洗ふ」は元々夏の季語。かつては特別な行事でもあったそうです。高温多湿の日本では、特に気持ちがさっぱりします。失敗した悔しさや悲しさまでもシャワーで洗い流されていく様子がよく伝わります。
しかたなくおふろにはいるこどもの日 都立立川国際中等教育学校附属小学校 二年 AMGALAN BILIG
不思議な句です。楽しい一日でお風呂に入りたくないのか、菖蒲の香りは苦手だけど伝統だからしかたないのかなど、「しかたなく」の言葉で様々なことを想像させます。
いますぐにはしりだしたいとかげかな 世田谷区立桜丘小学校 三年 濱﨑 葵
このとかげは少し臆病なのか、それともまだ幼いのか。シュッと逃げることはしないけれども、すぐにも逃げたそう。作者は、とかげの様子をじっと見て、今のとかげの気持ちを読み取りました。
砂利道で日焼けしたうで祖母に貸す 江東区立平久小学校 六年 小松原彩
足元の悪い道を、祖母と一緒に歩いている。小さい頃は手を引かれていたのに、今は日に焼けた自分の腕が祖母を支えている。誇らしいような、照れくさいような夏の日のひとコマが見える句です。
蚊の声で夢の続きを逃したり お茶の水女子大学附属中学校 二年 杉本那瑠
もうすこし寝たいけど、蚊の羽音に邪魔されて、起こされてしまいました。折角素敵な夢を見ていたのに、続きを見られなくなってしまった残念な気持ちが素直に表されています。
父がつくる雑煮の味は母の味山 口大学教育学部附属光中学校 三年 久保めぐみ
ご両親仲睦まじく過ごしていた様子が目に浮かびます。父がつくるお雑煮は自然と母の味になっていたのでしょう。特別なお雑煮ですね。家族思いの優しいお父さん。心和む俳句です。